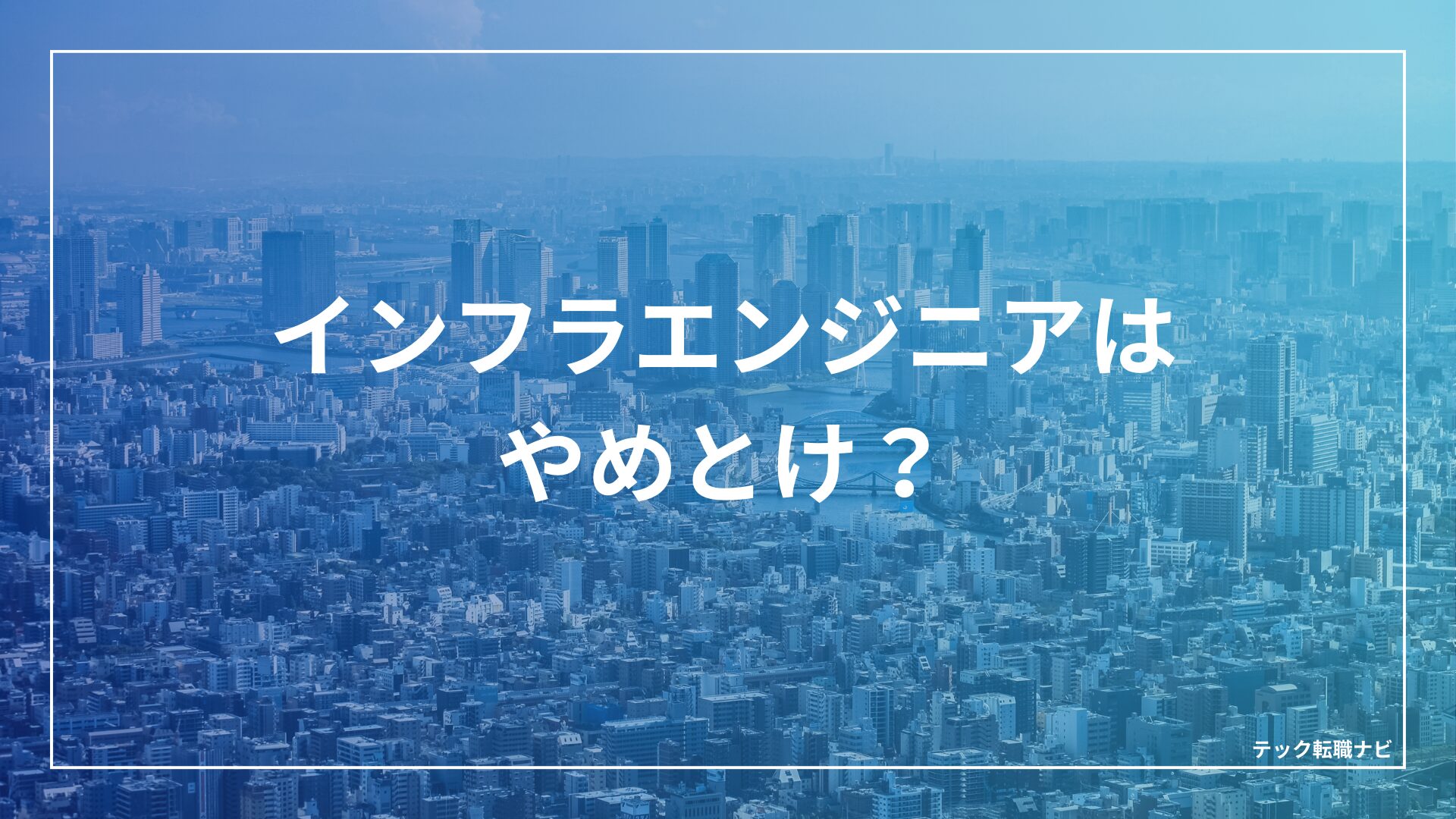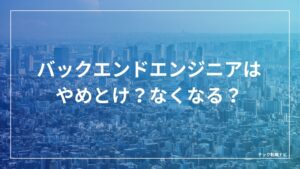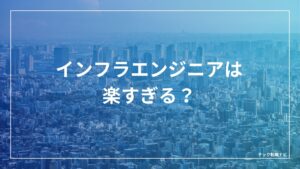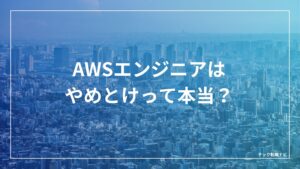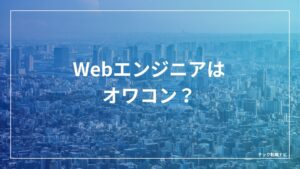「インフラエンジニアはやめとけと言われるってことは大変ってこと?」
「インフラエンジニアに自分は向いているのだろうか?」
「インフラエンジニアやめとけと言われる理由を知りたい」
インフラエンジニアとしてキャリアを築いていきたいと考えている人にとって、こうした悩みや不安を感じることがあるかもしれません。
インフラエンジニアはシステムやサービスを支える重要な役割を担う反面、「きつい」と言われることもあります。
長時間の勤務や高い責任感が求められる場面もあり、不安を感じることもあるかもしれません。
しかし、インフラエンジニアは社会に欠かせない存在であり、すぐになくなる仕事ではありません。
むしろ、技術が進化し続ける中で、より専門性が求められる職種として重要性を増しています。
また、困難な状況を乗り越えたときに得られる達成感や、自分の手で社会を支えているという実感は、この仕事ならではのやりがいと言えるでしょう。
この記事では、インフラエンジニアが「やめとけ」と言われる理由を5つ挙げ、それぞれ具体的な解決策を解説します。
また、この仕事に向いている人の特徴についても触れ、ご自分のキャリアを見つめ直すきっかけをご提供します。
インフラエンジニアとしてのキャリアを考え、悩んでいる方にとって、有益な情報となるはずです。
迷っている間に
選ばれる枠は埋まっていく
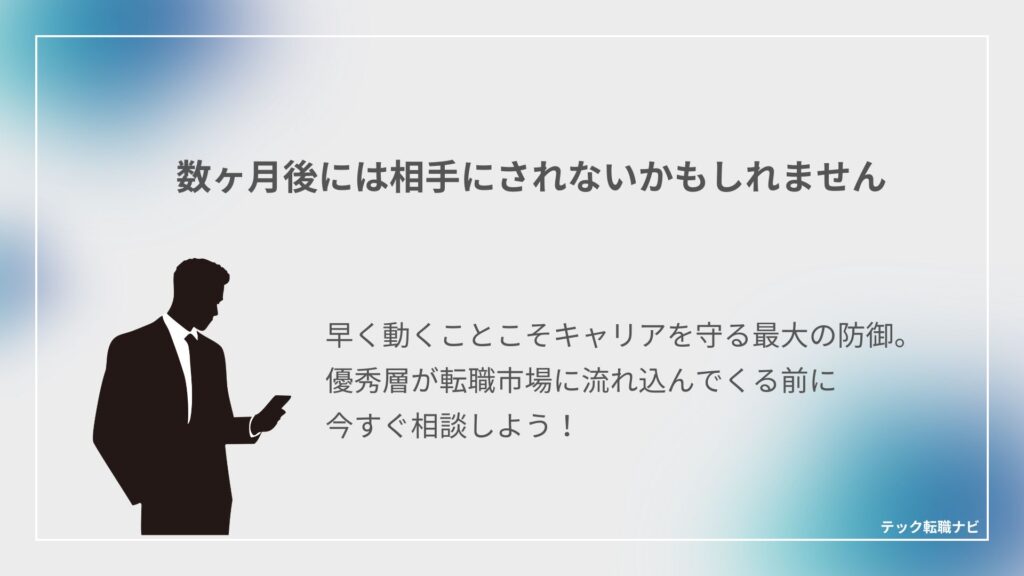
AIやChatGPTの普及により、エンジニアに求められる役割は静かに変わりつつあります。
現場でもAIが活用される領域が日に日に増え、「このままでいいのか」と不安に感じつつ、目の前の業務に忙殺されながら「なんとなくまだ大丈夫だろう」と動けずにいるエンジニアは多いのではないでしょうか。
私も10年前、クラウド化の波が押し寄せ始めたころ、「このままでは時代に取り残される」と焦りまくった経験があるので、気持ちはとてもよくわかります。
私の場合、このままではだめだと転職エージェントに相談したことで、流れを変えることができました。
たった1時間の面談で、自分の強みや可能性、そしてどうキャリアを発展させていくべきかに気づかされ、結果的に転職で年収は300万円以上アップ。黎明期にクラウド人材として評価されることで、社内外でのチャンスも大きく広がりました。
“早く動いた”ことこそが、自分のキャリアを守った最大の要因だったのです。
そして今──
あのとき以上の変化が、静かに、しかし確実に進んでいます。
マイクロソフトをはじめとするビッグテック企業が優秀なエンジニアを大量にリストラし、最前線で活躍していた優秀なエンジニアたちが転職市場に流れ込んでいます。
この先、彼らと比較された瞬間に“選ばれない”という現実がシビアに突きつけられるでしょう。
だからこそ、転職エージェントが相手をしてくれる今のうちに自分の現在地を確認しておくことが重要です。
転職するかどうかは、そのあと決めればいい。今後のキャリアの選択肢を持っておくことこそが、最大の防御力です。まずは、自分が“今の市場でどう見られているか”を知ることから始めてください。
あとで後悔しないために、“チャンスのある今”を逃さないでください。転職エージェントは無料で利用できるので上手く活用して、明るい未来を手繰り寄せましょう。
ITエンジニアで相談するなら
| サービス名 | 特徴 |
|---|---|
テックゴー | 年収UP条件UP・ スピード転職なら 強みが言語化できてない人や 忙しいエンジニアに◎ \ サポートが充実 / 公式サイト |
Beyond Career | 技術理解のある人に 相談したいなら キャリアの方向性が定まらない人に◎ 悩み段階でも相談OK \ とりあえず相談 / 公式サイト |
アクシスコンサルティング | コンサル転職を 目指すなら 選考対策がすごすぎる Big4や大手ファーム実績多数 \面接で勝てる自分になる/ 公式サイト |
転職エージェントは複数登録して問題ありません。担当者との相性もあるので、むしろ積極的に2~3社に登録・面談し、利用したいと思えるエージェントを見つけましょう。
インフラエンジニアはやめとけ?その理由とは
インフラエンジニアやめとけな理由① 障害対応で時間外対応が求められるから
インフラエンジニアの業務では、システム障害が発生した場合に時間外対応が求められることがあります。
ITインフラは非常に複雑で、多くの要素が絡み合っているため、原因の特定に時間がかかることも少なくありません。
さらに、原因が特定できても、修復作業や再発防止策の実施が必要になるため、対応が長引くケースも多々あります。
例えば、金融機関や通信インフラの障害では、短時間で解決しなければ多くのユーザーに影響を与えるため、プレッシャーが非常に大きくなります。
影響範囲が広いため、現場の判断ミスが許されないという精神的な負担も伴います。
こうした環境では、迅速に動けるスキルと冷静な判断力が求められるため、負担を感じやすいことは否めません。
こうした緊急対応やそのプレッシャーから、インフラエンジニアはやめとけと言われる場合があります。
そんなインフラエンジニアですが、この負担を軽減するために、効果的な取り組みをご紹介します。
まず、原因特定スキルを向上させることが重要です。
日常業務の中でトラブルシューティングの練習を繰り返したり、障害対応のシミュレーションを行うことで、実際の場面でも冷静に対応できるようになります。
また、障害対応時に役立つツールの活用も欠かせません。
ログ解析ツールや監視システムを事前に熟知しておくことで、障害発生時に迅速に状況を把握できるようになります。
こういったツールはいざという時の助けになりますので、普段から上司やステークホルダーに啓もう活動をし、上申して導入しておくことが大切です。
さらに、自己管理スキルを磨くことも大切です。
障害対応が長引く可能性がある場合には、短時間でも休息を取る工夫をすることで、集中力を維持しやすくなります。
例えば、仮眠を取るための環境を整えておくことや、リフレッシュのための軽い運動を取り入れると効果的です。
スキルアップを継続する姿勢も負担軽減に繋がります。
知識や技術力を高めることで、「自分はできる」という自信を持てるようになり、障害対応時の精神的な余裕が生まれます。
また、職場環境の選択も重要です。
障害が発生した際にチームで分担して作業を行える職場では、負担が個人に集中することを防ぐことができます。
転職や職場選びの際には、このような環境が整っているかを確認するのも有効な手段です。
これらの取り組みを意識的に実践することで、時間外対応が求められるインフラエンジニアの仕事でも、負担を軽減しながらキャリアを続けることが可能になります。
インフラエンジニアやめとけな理由②重要な基盤なのでプレッシャーが大きい
インフラエンジニアは、社会や企業の基盤を支える重要な役割を担っています。
そのため、システム障害が発生すると、自分の判断や行動が多くの人々に影響を与える責任を感じる場面が多いです。
例えば、金融機関や通信インフラでトラブルが起きた場合、迅速かつ正確な対応が求められます。
差し迫った期限内にシステムを完成させたり、問題なく稼働するよう保守運用することが求められます。
インフラは問題なく動いて当たり前な部分もあり、ユーザーからの期待値も高いものがあります。
こうした環境下で「失敗できない」という強いプレッシャーを感じることも少なくありません。
ただ、このプレッシャーに向き合うための方法はあります。
まず、タスクの優先順位を明確にすることが大切です。
すべての問題を一度に解決しようとするのではなく、最も影響が大きい箇所から対応していきます。
一つずつ取り組むことで、精神的な負担が軽くなり、冷静な判断がしやすくなるでしょう。
また、大きな問題に直面したときは、解決すべきタスクを小さなステップに分けて進めるのも効果的です。
一つずつクリアしていくことで達成感が得られ、気持ちに余裕が生まれます。
日常的にリフレッシュの時間を取ることも重要です。
短時間でも、軽い運動や深呼吸をするだけで心が落ち着きます。
こうしたちょっとした工夫が、プレッシャーを和らげる助けになります。
さらに、知識やスキルを高める努力もプレッシャーを軽減する大きなポイントです。
「自分はできる」と思える感覚があるだけで、気持ちがずいぶん楽になるはずです。
そして、問題を一人で抱え込まず、周囲に相談することも忘れてはいけません。
同僚や上司に早めに話すことで、新たな視点が得られることもありますし、負担を分け合えることもあります。
これらの方法を実践することで、責任感の強い仕事の中でもプレッシャーをうまくコントロールできるようになるでしょう。
大きな責任を担う仕事だからこそ、その分得られるやりがいや成長も大きいものです。
インフラエンジニアやめとけな理由③最新技術をキャッチアップしていく必要がある
インフラエンジニアの仕事では、技術の進化に対応し続けることが求められます。
新しい技術が次々と登場する中で、既存の知識やスキルが短期間で通用しなくなる場面も少なくありません。
例えば、クラウド技術やコンテナ技術が普及する中、従来のオンプレミス環境の知識だけでは業務に支障をきたすことがあります。
さらに、サイバーセキュリティの分野では、新たな脅威に対応するための知識が日々更新されており、これらを学び続ける必要があります。
技術の変化に追いつけないという不安が、インフラエンジニアを続けることに対する抵抗感につながることも多いでしょう。
しかし、この課題に対処する方法は存在します。
まず、自分に合った効率的な学習方法を見つけることが重要です。
オンラインコースや技術ブログを活用することで、時間のない中でも必要な知識を手軽に学べるようになります。
また、短い時間で学習できる動画教材やハンズオン形式のトレーニングを取り入れると、実務にも役立つ知識が得られるでしょう。
次に、学習の優先順位を明確にすることも重要です。
インフラエンジニアとして必要なスキルは多岐にわたりますが、すべてを習得する必要はありません。
現在の業務や将来のキャリアに直結する分野を選び、重点的に取り組むことで、効率的にスキルアップが図れます。
また、同業者との交流を通じて、最新の情報や実践的な知識を得ることも効果的です。
エンジニア向けの勉強会やコミュニティイベントに参加すれば、自分では気づかなかった学びのチャンスや視点が得られます。
他のエンジニアがどのように技術の進化に対応しているかを知ることで、新たなモチベーションにもつながるでしょう。
さらに、日々のスケジュールに学習時間を組み込むことで、継続的に学べる環境を作ることができます。
無理のないペースで週に1〜2時間を確保し、学ぶ習慣を身につけることで、プレッシャーを軽減できます。
実務を通じて新しい技術を試す機会を積極的に作ることも、自信を深める一助となります。
技術の進化はエンジニアにとって大きな挑戦ですが、学び続ける姿勢を持つことで、自分の価値をさらに高めることができるでしょう。
このような取り組みが、将来のキャリアを広げるきっかけとなるはずです。
インフラエンジニアやめとけな理由④客先常駐を求められる職場も多い
インフラエンジニアの働き方として、客先常駐が求められるケースが多くあります。
特にシステムインテグレーター(SIer)に所属するエンジニアは、クライアント先で業務を行うことが多く、その環境に順応する柔軟性が必要です。
客先常駐では、クライアントの施設や環境で働くため、それぞれ異なる企業文化やルールに適応する必要があります。
頻繁に勤務地が変わる場合には、通勤や生活リズムへの影響が生じることもあります。
こうした環境変化に対応するのは簡単ではなく、負担を感じる場面も少なくありません。
しかし、客先常駐の働き方には、大きな成長の機会も含まれています。
特に、実際の環境に直接触れられることは貴重な経験です。
教科書やトレーニングだけでは学べない、リアルな業務システムや運用フローに触れることで、実務的なスキルが確実に向上します。
複数のプロジェクトや業界を経験することで、知識だけでなく、実践的な問題解決能力を養うことができるのです。
さらに、クライアントとの関係構築を通じて、コミュニケーション能力や交渉力が自然と磨かれます。
こうしたスキルは、将来的にマネジメントやコンサルティングの分野で役立つだけでなく、どのような職場でも活用できる汎用的な能力です。
また、異なる業界や企業のシステムに触れることで、特定の分野に偏らない広い視野を持つことができます。
これにより、他のエンジニアにはない独自の知見を持ち、自分の市場価値を高めることが可能です。
客先常駐には確かに課題もありますが、その中で得られる経験やスキルは非常に貴重です。
この働き方を活かすことで、インフラエンジニアとしてのキャリアに大きなプラスをもたらすことができるでしょう。
インフラエンジニアやめとけな理由⑤夜勤や休日出勤が求められる職場もある
インフラエンジニアの仕事では、夜勤や休日出勤が必要になるケースがあります。
特に、システムの更改やメンテナンスは、利用者が少ない時間帯を選んで行われるため、深夜や休日に対応することが一般的です。
また、年末年始やゴールデンウィーク、お盆休みといった長期休暇中に作業が計画されることも多く、周りが休みを楽しんでいるタイミングで仕事をする場面も少なくありません。
このような勤務形態では、家族や友人と休みを合わせにくいという課題があります。
例えば、長期休暇を利用した旅行やイベントに参加しづらく、生活のリズムが周囲と異なることで孤独感を感じる場合もあるでしょう。
一方で、周りと違うタイミングで休みを取れることをメリットと感じる人もいます。
平日に休暇を取れる場合、観光地や商業施設が混雑していない空いている時間に過ごせるため、効率的に休暇を楽しむことができます。
また、独自のペースでスケジュールを調整できるため、自分の時間を有意義に使えると感じる人もいるでしょう。
このような勤務スタイルにはデメリットもありますが、環境に適応し、自分なりの働き方を工夫することでストレスを軽減できます。
たとえば、休暇を前もって計画しておくことで、仕事とのバランスを取りやすくなります。
また、家族や友人と予定をすり合わせ、短時間でも有意義に過ごす工夫をすることも重要です。
夜勤や休日出勤が求められる職場では、自分のライフスタイルとの相性をよく考え、長期的に働きやすい環境を選ぶことが大切です。
インフラエンジニアに向いている人の特徴
インフラエンジニア向いてる人①問題解決能力が高い人
インフラエンジニアの仕事では、問題解決能力が非常に重要です。
システム障害が発生した際や、パフォーマンスの低下が見られる場合、迅速かつ的確に原因を特定し、対応する必要があります。
また、トラブルシューティングでは複数の選択肢から最適な解決策を選ぶ場面も多く、論理的に考える力が求められます。
例えば、ネットワーク障害が発生した場合には、通信経路や機器の設定状況を一つ一つ確認しながら、問題の根本原因を探る必要があります。
こうした課題に対処するためには、冷静さと集中力を持って対応できる能力が欠かせません。
さらに、課題を解決した後には、再発防止策を講じることも求められます。
そのため、一度の解決で終わらず、長期的な視点で物事を考える力が必要です。
問題解決能力が高い人は、これらの状況でも落ち着いて対処できるため、インフラエンジニアとして活躍しやすいと言えます。
また、この能力は業務だけでなく、キャリア全体においても強みになります。
インフラエンジニア向いてる人②ストレス耐性が強い人
インフラエンジニアは、高いストレス耐性を持つ人が活躍しやすい職種と言えます。
業務には、システム障害やトラブルの対応が含まれ、緊張感のある場面に直面することが少なくありません。
特に、影響範囲が広い障害が発生した場合には、迅速な対応と正確な判断が求められるため、プレッシャーを感じることも多いでしょう。
さらに、技術の進化に常に対応しなければならない業界の特性上、新しい知識を学び続ける必要があり、その過程で不安や焦りを感じる場面もあるかもしれません。
こうした状況でも冷静さを保ち、計画的に行動できるストレス耐性は、インフラエンジニアとしての重要な資質です。
例えば、障害対応中に時間がかかる問題に直面しても、焦らずに一つずつ解決策を試すことで、最終的に問題を解決へ導ける人は非常に頼りにされます。
また、業務外でのストレス管理も大切です。
自分なりのリフレッシュ方法を見つけて実践することで、精神的なバランスを保つことができます。
これにより、困難な状況でも継続的にモチベーションを維持し、パフォーマンスを発揮できるでしょう。
ストレス耐性が高い人は、このような環境でも安定した結果を出すことができるため、インフラエンジニアとしての成長につながります。
インフラエンジニア向いてる人③チームで協力できる人
インフラエンジニアの仕事では、チームで協力する能力が非常に重要です。
システムの設計、構築、運用、トラブル対応において、一人で対応する場面は限られており、多くの場合、複数のエンジニアが連携して業務を進めます。
例えば、大規模なシステムの更改やインフラの構築では、ネットワーク、サーバー、データベースといった専門分野のエンジニアが協力し、全体のバランスを考えながら作業を進める必要があります。
また、トラブル対応では、それぞれのエンジニアが持つ専門知識を共有し合い、迅速に解決策を導き出すことが求められます。
チームで協力できる人は、情報共有や意見交換を円滑に行い、作業効率を高めることができます。
さらに、他のメンバーの意見を尊重し、柔軟に対応できる姿勢を持つことで、信頼関係を築きやすくなります。
この信頼関係は、プロジェクトを円滑に進めるだけでなく、より良い結果を生み出す土台となります。
また、チームで働く中で学べることも多くあります。
他のエンジニアの考え方やスキルを学ぶことで、自分自身の成長にもつながります。
チームでの協力を重視できる人は、インフラエンジニアとして安定した成果を上げるだけでなく、より大きな責任を担うポジションで活躍する可能性も広がるでしょう。
インフラエンジニアがおすすめな理由
インフラエンジニアおすすめな理由①社会に欠かせない職種であるから
インフラエンジニアは、社会に欠かせない存在です。
システムやネットワークは、企業や個人の生活に密接に関わっており、日々の業務や活動を支えています。
例えば、オンラインショッピング、金融取引、交通機関の運行など、すべての基盤にはインフラエンジニアの努力と活躍があってこそです。
これらが円滑に動くことで、社会全体が成り立っていると言っても過言ではありません。
このような仕事に携わることで、間接的に多くの人々の生活を支えているというやりがいを感じられるでしょう。
さらに、重要な基盤を担う職種であるため、スキルを持つエンジニアは需要が高く、安定した雇用が期待できます。
インフラエンジニアとしての経験は、他のIT分野や管理職へキャリアを広げる際にも役立つため、長期的な視点で見ても価値のある職種です。
インフラエンジニアおすすめな理由②技術力を活かせる環境とやりがい
インフラエンジニアの仕事は、技術力を存分に活かせる環境である点が大きな魅力です。
システム設計や構築、運用といった幅広い業務の中で、自分の専門スキルを活用しながら成果を上げることができます。
例えば、ネットワークの最適化やサーバーの効率的な構築など、エンジニアの技術力がそのまま業務の成果に直結するため、大きな達成感を得られるでしょう。
また、常に新しい技術が求められる業界であるため、学び続ける姿勢があれば、スキルアップを実感しやすい職場でもあります。
実際の業務では、課題解決のプロセスを通じて、自分の技術力がどれだけ向上しているかを具体的に確認することができます。
このプロセスで得られるやりがいは、他の職種では味わえない特別なものです。
さらに、企業やプロジェクトによっては、規模の大きなシステムや複雑なネットワークに携わる機会も多くあります。
こうした経験は、他のエンジニアとの差別化にもつながり、自分の市場価値を高めることができます。
また、業務の中で築かれるチームとの協力関係やクライアントとの信頼関係は、技術力だけでなく、エンジニアとしての成長を促進する要因となるでしょう。
インフラエンジニアは、自分の能力を直接反映できる職種だからこそ、成長と達成感を同時に得られる仕事といえます。
インフラエンジニアオススメな理由③年収や成長の可能性が広がるキャリアパス
インフラエンジニアとして働くことで、年収や成長の可能性が広がる多様なキャリアパスを選択できます。
まず、インフラエンジニアの経験を積むことで、クラウド技術やDevOpsといった最新の技術領域にスキルをシフトさせることが可能です。
現在、多くの企業がクラウド移行を進めており、この分野での知識や経験は非常に高い需要があります。
特に、AWSやAzure、Google Cloudといった主要なクラウドプラットフォームのスキルは、市場価値を大きく向上させる要因となります。
また、インフラエンジニアとしての経験は、プロジェクトマネージャーやITコンサルタントといった上流工程のポジションへ進む際にも役立ちます。
これらのポジションでは、技術力だけでなく、チームのマネジメント能力やクライアントとの交渉スキルが求められますが、インフラエンジニアのバックグラウンドを持つ人材は、こうした能力を自然に磨いていける環境にいます。
さらに、独立してフリーランスとして働く道もあります。
フリーランスのエンジニアは、自分で案件を選べる自由度が高く、高収入を狙うことも可能です。
特に、専門性の高いスキルや実績を持つエンジニアであれば、より高単価の案件を受注できるチャンスが広がります。
このように、インフラエンジニアとしての経験は、キャリアの幅を広げるだけでなく、年収を大きく向上させる可能性も秘めています。
自分の将来を見据えたキャリアパスを選ぶことで、さらに充実した働き方を実現できるでしょう。
インフラエンジニアとしてのキャリアを考える
インフラエンジニアはなくならないのか?
インフラエンジニアという職種が将来的になくなるのではないかと、不安を抱える人もいるかもしれません。
確かに、クラウド技術の進化や自動化ツールの普及によって、従来型のオンプレミス環境を管理する仕事は減少傾向にあります。
しかし、インフラエンジニアが完全になくなることは考えにくいでしょう。
理由の一つは、クラウドや仮想化技術の運用には、依然として高度な専門知識を持つエンジニアが必要であることです。
クラウドプラットフォームを管理する際には、システム全体を俯瞰し、適切に構築・運用するスキルが欠かせません。
さらに、サイバーセキュリティの重要性が増している現代では、ネットワークやサーバーの安全性を確保するための専門的な知識が必要です。
インフラエンジニアは、これらの新しい技術やトレンドに対応することで、需要がむしろ高まる可能性もあります。
また、物理的なインフラが完全になくなるわけではありません。
特に、通信業界や金融機関、製造業などでは、オンプレミス環境が必要不可欠なケースが多く、これらの分野では引き続きインフラエンジニアが求められるでしょう。
さらに、クラウドや自動化ツールの導入が進んだとしても、それらを正しく設定し、適切に運用するためには、人間の判断が不可欠です。
インフラエンジニアの役割は、これまで以上に高度で専門的なものへと変化していますが、これがなくなることはなく、新しい形で必要とされ続ける職種といえます。
このように、インフラエンジニアは時代の変化に適応しながら、その価値を進化させ続けることができる職種です。
インフラエンジニアからのキャリアパス例①インフラエンジニアを極める
インフラエンジニアのキャリアの中で、自分の専門分野を深めることは、非常に価値のある選択肢です。
システムやネットワークの設計、構築、運用において、特定の分野を徹底的に追求することで、他のエンジニアとの差別化が可能になります。
例えば、ネットワークエンジニアとしてスイッチやルーターの知識を極めたり、大規模なデータセンターの設計に特化することができます。
また、サーバーエンジニアとしては、仮想化技術やストレージ設計に強みを持ち、特定の技術領域でエキスパートとして活躍することが可能です。
インフラエンジニアを極めることで、企業内で重要な役割を担うことができます。
例えば、技術力を認められて「リードエンジニア」や「プリンシパルエンジニア」といった上級ポジションに就くことができます。
こうした役職では、新技術の導入やプロジェクトの技術的な指揮を任されることが多く、キャリアの安定性や報酬面での向上が期待されます。
さらに、専門知識を活かして技術セミナーの講師を務めたり、技術書の執筆を行うことで、業界内での認知度を高めることも可能です。
こうした活動を通じて、自分の価値をさらに高めることができます。
また、ハードウェアベンダー(Cisco、VMware、Red Hatなど)の認定資格を取得することで、国際的に通用するスキルを証明することもできます。
地道な努力が必要ですが、得られる達成感や安定したキャリアを考えると、インフラエンジニアを極める選択肢は非常に魅力的です。
インフラエンジニアからのキャリアパス例②クラウドエンジニア
インフラエンジニアの経験を活かしてクラウドエンジニアになることは、将来的な需要を見据えた有望な選択肢です。
クラウド技術は現在、多くの企業で採用が進んでおり、特にAWS、Azure、Google Cloudなどのプラットフォームに関連するスキルが求められています。
クラウドエンジニアの主な業務は、これらのプラットフォームを利用したシステムの設計、構築、運用です。
従来のインフラエンジニアのスキルを基盤に、クラウド特有の技術を学ぶことで、比較的スムーズに転向できます。
例えば、Infrastructure as Code(IaC)を使った構成管理や、自動化ツール(Terraform、Ansibleなど)の活用は、クラウドエンジニアには欠かせないスキルです。
また、マルチクラウド環境の管理ができるスキルは、大規模な企業で特に重宝されます。
クラウドエンジニアとしてのキャリアパスは多様であり、クラウドアーキテクトやクラウドセキュリティの専門家といった高付加価値の役割に進むことも可能です。
さらに、リモートワークとの親和性が高いこともクラウドエンジニアの大きなメリットです。
クラウド環境はインターネット経由で管理できるため、働き方の自由度が増し、柔軟なライフスタイルを実現しやすくなります。
クラウドエンジニアを目指す際には、公式トレーニングや認定資格(AWS Certified Solutions Architect、Azure Administratorなど)の取得が役立ちます。
これらの資格は、学習の指針になるだけでなく、スキルの証明として転職活動やキャリアアップに大いに活用できます。
クラウドエンジニアとしてのスキルを身につけることで、インフラエンジニア時代の経験を次のキャリアに活かせる大きなチャンスを得られるでしょう。
インフラエンジニアからのキャリアパス例③DevOpsエンジニア
インフラエンジニアからDevOpsエンジニアへの転向は、特に最近のIT業界で注目されているキャリアパスの一つです。
DevOpsは、開発(Development)と運用(Operations)の連携を強化するアプローチであり、システム全体の効率化と信頼性向上を目指します。
DevOpsエンジニアとして働くには、インフラエンジニアのスキルに加えて、開発チームと運用チームをつなぐ役割を果たす能力が必要です。
たとえば、CI/CD(継続的インテグレーションとデリバリー)のパイプラインを構築するスキルが求められます。
さらに、コンテナ技術(DockerやKubernetes)の知識も重要です。
これらのツールを使うことで、アプリケーションの動作環境を標準化し、効率的な運用を実現できます。
DevOpsエンジニアのもう一つの特徴は、Infrastructure as Code(IaC)を活用してインフラ環境をコードで管理する点です。
TerraformやAnsibleなどのツールを使い、迅速な環境構築や変更の追跡が可能になります。
こうしたスキルを持つことで、従来のインフラエンジニアでは対応が難しいようなスピード感を持ったプロジェクトにも貢献できます。
DevOpsエンジニアは、企業内で非常に重要な役割を担うため、そのスキルセットが高く評価され、給与やキャリアアップの面でもメリットがあります。
また、新しい技術を積極的に導入する企業で働けるチャンスも多く、仕事のやりがいを感じやすい点も魅力です。
DevOpsエンジニアを目指すには、オンライン学習プラットフォームや認定資格(AWS Certified DevOps Engineer、CKAなど)を活用して、実務に役立つスキルを効率的に学ぶことがおすすめです。
こうしたスキルセットを持つことで、IT業界の最前線で活躍することが可能になります。
インフラエンジニアからのキャリアパス例④セキュリティエンジニア
セキュリティエンジニアは、インフラエンジニアの経験を活かせるキャリアの一つであり、特に近年需要が高まっています。
情報漏洩やサイバー攻撃のリスクが増加している現代において、システムやネットワークの安全性を確保する役割は非常に重要です。
セキュリティエンジニアは、システムの脆弱性を特定し、改善策を提案・実施することが主な業務です。
また、セキュリティポリシーの策定や、社員向けのセキュリティ教育を行うことも求められる場合があります。
この職種では、ネットワークセキュリティ、データ保護、脆弱性診断ツールの使用(NessusやQualysなど)のスキルが必要です。
インフラエンジニアとしての経験は、ネットワーク構築やサーバー管理の知識があるため、セキュリティエンジニアへの転向に有利に働きます。
さらに、クラウドセキュリティに関するスキルを習得することで、より幅広い案件に対応できるようになります。
セキュリティエンジニアは、エンドポイントセキュリティや侵入検知システム(IDS)の運用を担当することも多いです。
これらのスキルを磨くことで、専門性が高まり、キャリアの選択肢が広がります。
セキュリティエンジニアを目指す際には、CompTIA Security+、CISSP(Certified Information Systems Security Professional)などの資格が役立ちます。
これらの資格は、専門知識を証明するだけでなく、転職市場での競争力を高める要素となります。
セキュリティ分野での活躍は、企業や社会の安全を守るという意義深い仕事に携わる機会を提供してくれるでしょう。
インフラエンジニアからのキャリアパス例⑤プロジェクトマネージャ
プロジェクトマネージャ(PM)は、インフラエンジニアとしての経験を活かせる上流工程のキャリアパスです。
インフラエンジニアとして現場で得た知識や経験を基盤に、プロジェクト全体の計画や進行を管理する役割を担います。
PMの主な業務は、プロジェクトのスケジュール作成、予算管理、リソースの割り当て、そしてチームメンバーの調整です。
これに加えて、顧客やクライアントとのコミュニケーションを円滑に行い、プロジェクトの成功に向けた全体的な舵取りを行います。
このキャリアパスを選ぶ利点の一つは、プロジェクト全体を俯瞰できる立場に立てることです。
インフラエンジニアとして現場で培った技術的な視点を活かしつつ、プロジェクトの目的を達成するための戦略を構築できます。
また、PMはリーダーシップやマネジメントスキルを伸ばす絶好の機会を提供します。
チームメンバーをまとめ、プロジェクトを成功に導く過程で、リーダーとしてのスキルが磨かれるため、さらなるキャリアアップが期待できます。
PMとしての成功に必要なスキルには、タスク管理ツールの活用やプロジェクト管理手法の理解が含まれます。
たとえば、JIRAやTrelloなどのツールを使いこなし、進捗状況を正確に把握することが重要です。
また、アジャイルやウォーターフォールといったプロジェクト管理手法についての知識を深めることも必要です。
さらに、コミュニケーション能力も重要な要素です。
PMは多くのステークホルダーと関わるため、相手にわかりやすく状況を伝え、相互理解を促進するスキルが求められます。
プロジェクトマネージャを目指す際には、PMP(Project Management Professional)やITIL(Information Technology Infrastructure Library)といった資格を取得することで、転職市場での競争力を高めることができます。
PMとしてのキャリアは、インフラエンジニアとしての技術力とマネジメント力の両方を活かせるため、技術系からのステップアップを考えるエンジニアにとって魅力的な選択肢です。
また、この役割は他の分野にも転用可能なスキルセットを提供するため、長期的なキャリア設計においても大きなメリットをもたらします。
インフラエンジニアの経験を活かし、PMとして新たなキャリアを築くことで、仕事の幅と責任が広がり、やりがいを感じる機会が増えるでしょう。
インフラエンジニアを続けるべきかやめるべきか
自分に合った働き方を見つけるポイント
インフラエンジニアとしてのキャリアを続けるべきか、それともやめるべきかを判断する際には、自分に合った働き方を見つけることが重要です。
まず、自分がどのような環境で働きたいかを明確にする必要があります。
たとえば、夜勤や休日出勤の少ない職場を希望するのか、リモートワークを重視するのか、あるいは新しい技術に挑戦できる環境を求めるのかを考えることが大切です。
次に、現在の仕事で感じている不満やストレスの原因を特定しましょう。
それが業務内容なのか、職場環境なのか、あるいは人間関係なのかを明確にすることで、改善すべきポイントが見えてきます。
場合によっては、転職ではなく現職での交渉や環境改善で解決できることもあるでしょう。
また、自分のスキルや興味に合った分野に焦点を当てることも重要です。
クラウドやDevOpsといった最新技術に興味がある場合は、それを活かせる職場を探すことで、モチベーションを保ちながら働くことができます。
さらに、自分のキャリアの長期的な目標を考えることも必要です。
将来、管理職やコンサルタント、あるいはフリーランスとして働きたいと考えている場合、その目標に向けたキャリアパスが用意されている職場を選ぶことが大切です。
最後に、現職のインフラエンジニアとしての経験が自分の強みであることを認識しましょう。
これをベースに、より自分に合った働き方を見つけることが、続けるべきかやめるべきかの判断をする上で重要なポイントになります。
続ける場合に必要なスキルとマインドセット
インフラエンジニアとしてキャリアを続けるには、意識して努力を重ねることで習得できるスキルやマインドセットを強化することが重要です。
まず、技術力の向上が不可欠です。
クラウド技術は特に注目されており、AWSやAzure、Google Cloudといった主要なプラットフォームの認定資格を取得することで、実務で使える知識を体系的に身につけることができます。
こうした資格取得の過程で得られる知識は、自分の業務に役立つだけでなく、キャリアの選択肢を広げる要素にもなります。
また、自動化スキルの習得も重要です。
TerraformやAnsible、Docker、Kubernetesなどのツールを使った環境構築や運用は、今後さらに求められるスキルです。
オンライン学習プラットフォームやオープンソースのプロジェクトに参加することで、実際に手を動かしながらこれらのスキルを習得できます。
問題解決能力は、実務の中で自然と鍛えることが可能です。
障害対応やシステムトラブルに直面した際、原因の分析と解決プロセスを記録し、振り返りを行う習慣をつけることで、次回以降の対応をよりスムーズにすることができます。
さらに、仮想環境で障害をシミュレーションし、解決策を練習することで、自信と判断力を強化することができます。
コミュニケーション能力も、実際の業務で意識することで向上します。
クライアントや他部門と協力する場面では、専門用語を簡潔でわかりやすい言葉に変換して伝えることを心がけると、スムーズな意思疎通が可能になります。
また、プレゼンや報告の場で自分の意見をしっかりと伝える練習を重ねることで、対話スキルが磨かれます。
ストレス管理も重要なポイントです。
プレッシャーが大きい場面でも安定したパフォーマンスを発揮するには、適度にリフレッシュできる時間を意識して確保することが大切です。
日常的な軽い運動や趣味に時間を使うことで、仕事の負担を軽減し、精神的な余裕を持つことができます。
さらに、柔軟な考え方を持つことも必要です。
技術や業務環境が日々進化する中で、新しい変化を学びの機会と捉える姿勢が求められます。
自分の得意分野を磨きながら、業務の幅を広げる努力を続けることで、より多くのチャンスを掴むことができるでしょう。
こうしたスキルやマインドセットを意識して身につけることで、インフラエンジニアとしてさらに活躍の場を広げ、長期的に満足できるキャリアを築くことが可能になります。
やめる場合に役立つ転職戦略
インフラエンジニアのキャリアをやめると決めた場合でも、その経験を活かして次のステージに進むことができます。
転職を成功させるためには、適切な戦略を立てることが重要です。
まず、自分の経験やスキルを整理することから始めましょう。
これまで携わったプロジェクトや、解決した課題を具体的に振り返り、成果としてアピールできるポイントを明確にします。
例えば、ネットワークの最適化やサーバー構築、障害対応など、どの分野で実績を積んだかを整理することで、応募先企業への説得力が増します。
次に、キャリアの方向性を明確にすることが大切です。
クラウドエンジニアやDevOpsエンジニアへの転向を目指す場合は、既存のスキルに加えて、新しい技術を学ぶ計画を立てます。
一方で、ITコンサルタントやプロジェクトマネージャーを目指す場合には、技術力に加えてマネジメントやコミュニケーションの経験をアピールすることが重要です。
さらに、求人数や業界動向をリサーチすることで、効率的に転職活動を進めることができます。
特にクラウドやセキュリティ関連の分野は需要が高く、インフラエンジニアとしての経験を活かせる求人が多く見つかるでしょう。
転職エージェントを活用することで、業界特有の情報を収集し、適切なサポートを受けることも可能です。
また、スキルアップの計画を立てて実行することも成功の鍵です。
例えば、クラウド関連の資格(AWS認定資格やGoogle Cloud認定資格)を取得することで、新しい分野へのスムーズな転向が期待できます。
資格取得を目標にすることで、学習の方向性が明確になり、面接でも自信を持ってスキルをアピールできます。
最後に、自分の強みを最大限活かす自己PRを準備することが重要です。
インフラエンジニアとしての経験が、次の職種でどのように貢献できるかを具体的に示すことで、転職先企業に対して明確な価値を伝えることができます。
これらの戦略を実践することで、インフラエンジニアとしての経験を活かしながら、新しいキャリアへの一歩を踏み出すことができるでしょう。
まとめ:インフラエンジニアはやめとけではなく可能性の広がる仕事
インフラエンジニアという職種には、やりがいや成長の機会が多くある一方で、夜勤や休日出勤、技術の進化への対応といった課題も存在します。
これらの負担が「やめとけ」と言われる理由につながることもありますが、それを上回るメリットや可能性を見出すことも十分に可能です。
インフラエンジニアとしてキャリアを続ける場合には、クラウドや自動化ツールのスキルを学ぶこと、柔軟な思考と問題解決能力を磨くことが重要です。
また、日々の業務の中で新しい技術に挑戦し、自分の価値を高める努力を続けることで、さらに成長できる職種でもあります。
一方で、キャリアを転向する場合でも、インフラエンジニアとしての経験は非常に貴重です。
クラウドエンジニアやプロジェクトマネージャー、ITコンサルタントなど、新しい分野に挑戦する際に大きな武器となります。
自分の実績をしっかりと整理し、新たな目標に向かって転職活動を進めることで、より良い未来を切り開けるでしょう。
インフラエンジニアという仕事は、簡単な道ではありませんが、その分やりがいも大きい職種です。
自分に合った働き方やキャリアパスを見つけることで、充実した仕事と生活を両立させることができるでしょう。
この記事を通じて、自分の現状を見つめ直し、今後のキャリアを考える際の参考になれば幸いです。