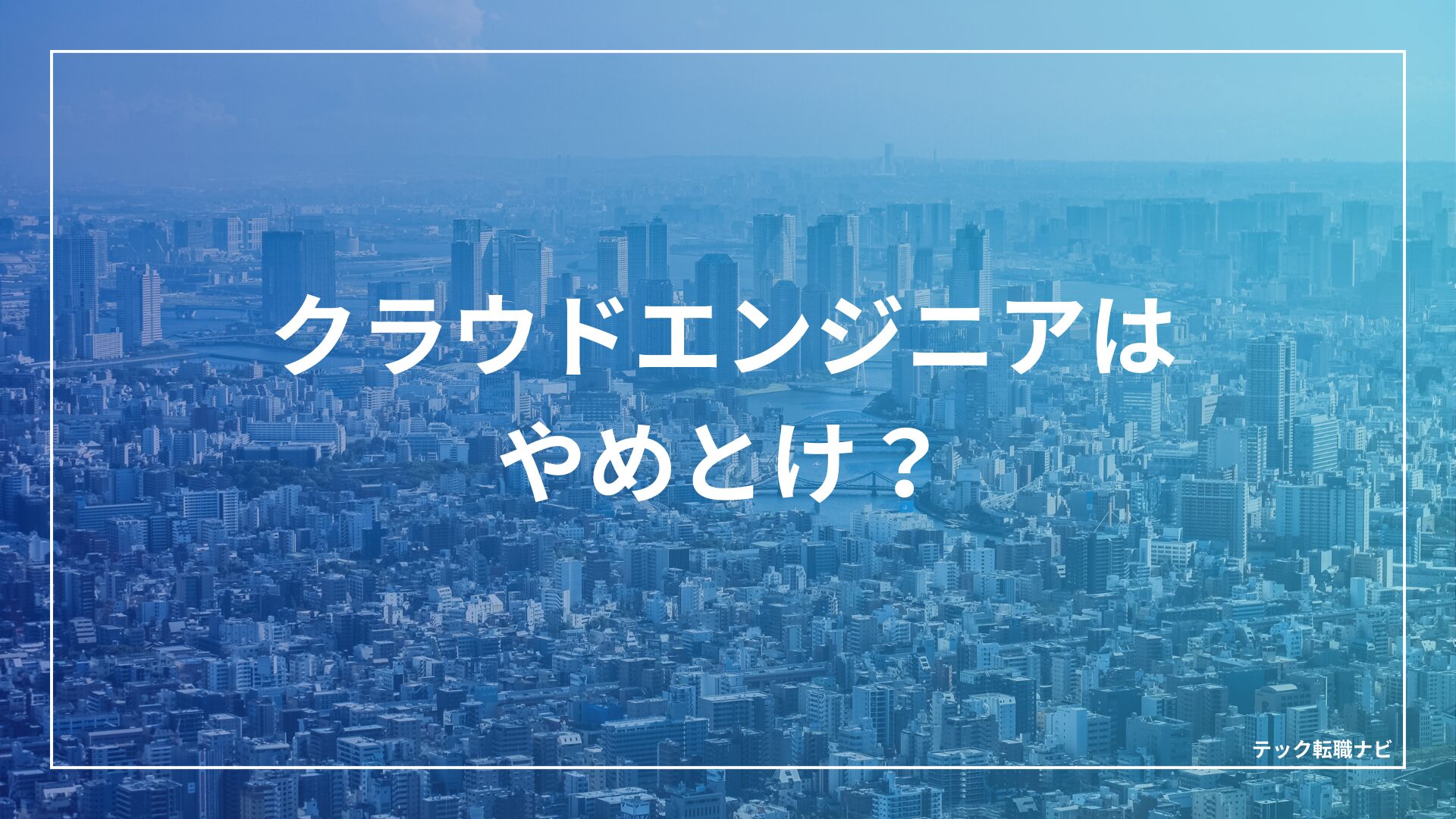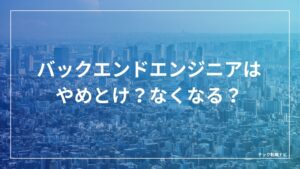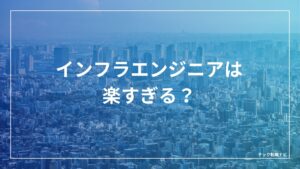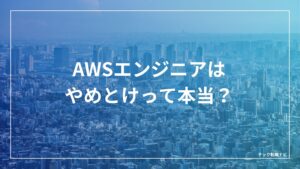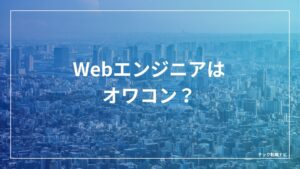「クラウドエンジニアはやめとけって本当?」
「クラウドエンジニアはきついと聞いたけど実際どう?」
「クラウドエンジニアの楽しい部分ってどんなところ?」
クラウドエンジニアへの転職を考えている人にとって、仕事内容の難しさや責任の重さ、将来性に関する不安は尽きないものです。
実際に、「やめとけ」と言われる理由には納得できる部分もありますが、一方で、この職種には楽しいと感じるやりがいや大きな成長機会もあるのです。
クラウドエンジニアの仕事は一見ハードルが高く見えますが、ポイントを押さえればキャリアパスを確立でき、後悔しない選択ができます。
この記事では、クラウドエンジニアの「やめとけ」と言われる理由を掘り下げつつ、この職種で成功するためのポイントや楽しいと感じる人の特徴を解説します。
これからクラウドエンジニアを目指すか迷っている方に役立つ情報をお届けします。
迷っている間に
選ばれる枠は埋まっていく
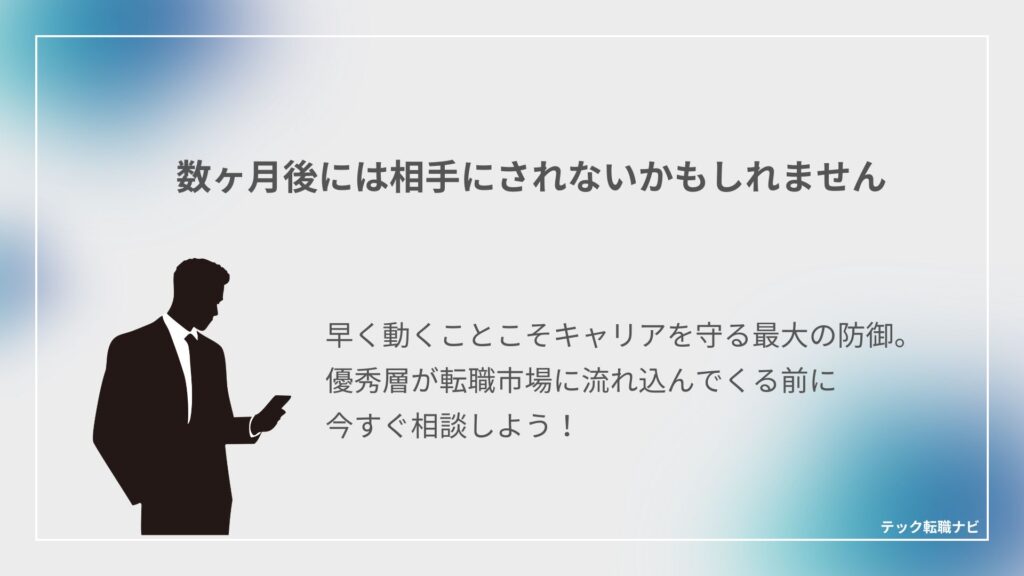
AIやChatGPTの普及により、エンジニアに求められる役割は静かに変わりつつあります。
現場でもAIが活用される領域が日に日に増え、「このままでいいのか」と不安に感じつつ、目の前の業務に忙殺されながら「なんとなくまだ大丈夫だろう」と動けずにいるエンジニアは多いのではないでしょうか。
私も10年前、クラウド化の波が押し寄せ始めたころ、「このままでは時代に取り残される」と焦りまくった経験があるので、気持ちはとてもよくわかります。
私の場合、このままではだめだと転職エージェントに相談したことで、流れを変えることができました。
たった1時間の面談で、自分の強みや可能性、そしてどうキャリアを発展させていくべきかに気づかされ、結果的に転職で年収は300万円以上アップ。黎明期にクラウド人材として評価されることで、社内外でのチャンスも大きく広がりました。
“早く動いた”ことこそが、自分のキャリアを守った最大の要因だったのです。
そして今──
あのとき以上の変化が、静かに、しかし確実に進んでいます。
マイクロソフトをはじめとするビッグテック企業が優秀なエンジニアを大量にリストラし、最前線で活躍していた優秀なエンジニアたちが転職市場に流れ込んでいます。
この先、彼らと比較された瞬間に“選ばれない”という現実がシビアに突きつけられるでしょう。
だからこそ、転職エージェントが相手をしてくれる今のうちに自分の現在地を確認しておくことが重要です。
転職するかどうかは、そのあと決めればいい。今後のキャリアの選択肢を持っておくことこそが、最大の防御力です。まずは、自分が“今の市場でどう見られているか”を知ることから始めてください。
あとで後悔しないために、“チャンスのある今”を逃さないでください。転職エージェントは無料で利用できるので上手く活用して、明るい未来を手繰り寄せましょう。
ITエンジニアで相談するなら
| サービス名 | 特徴 |
|---|---|
テックゴー | 年収UP条件UP・ スピード転職なら 強みが言語化できてない人や 忙しいエンジニアに◎ \ サポートが充実 / 公式サイト |
Beyond Career | 技術理解のある人に 相談したいなら キャリアの方向性が定まらない人に◎ 悩み段階でも相談OK \ とりあえず相談 / 公式サイト |
アクシスコンサルティング | コンサル転職を 目指すなら 選考対策がすごすぎる Big4や大手ファーム実績多数 \面接で勝てる自分になる/ 公式サイト |
転職エージェントは複数登録して問題ありません。担当者との相性もあるので、むしろ積極的に2~3社に登録・面談し、利用したいと思えるエージェントを見つけましょう。
クラウドエンジニアはやめとけ?きついと言われる理由と現場の実態
クラウドエンジニアやめとけな理由①技術の進化が速く学び続ける必要がある
クラウドエンジニアとして働く上で、技術の進化が非常に速い点は避けて通れません。
クラウドサービスの大手であるAWSやGoogle Cloud、Microsoft Azureは、年に何百もの新機能を追加しています。
これらに追いつくためには、新しい技術を学び続ける時間とエネルギーが必要です。
特に、現場では業務が忙しい中で学習の時間を確保することが求められるため、効率的な学び方を身につけることが鍵となります。
新しいサービスやツールが次々に登場し、既存の技術がすぐに陳腐化することもあります。
これに対応するためには、常に学び続ける姿勢が求められます。
たとえば、クラウド環境の構築において新しいセキュリティ対策が必要になった場合、それを迅速に理解し適用することが求められるのです。
勉強の時間を確保する必要があり、プライベートな時間を圧迫するケースも少なくありません。
特に家族との時間や趣味に使う時間を確保するのが難しいという声も聞かれます。
仕事と学習のバランスをうまく取る工夫が必要です。
高度な資格の取得も、クラウドエンジニアには欠かせません。
AWSのソリューションアーキテクトやGoogle Cloudのプロフェッショナルエンジニア資格などは、多くのエンジニアが挑戦するものですが、合格には相当の努力が必要です。
これらの資格を持っているかどうかが、キャリアの選択肢を大きく左右することも少なくありません。
特に、大規模なシステムを扱う企業では、最新技術を取り入れることで競争力を保つ必要があり、エンジニアに求められるスキルも高度になります。
クラウドのトレンドに取り残されないよう、自己研鑽を怠らないことが必須です。
このような状況は、成長を続けるエンジニアには魅力的ですが、学習に対してモチベーションを維持することが難しい人には大きな壁となるでしょう。
一方で、常に新しい知識を得ることに喜びを感じる人にとっては、刺激的で飽きのこない職種とも言えます。
クラウドエンジニアやめとけな理由②責任の重さがプレッシャーになる
クラウドエンジニアの仕事は、企業の基盤となるインフラを支える重要な役割を担います。
例えば、オンラインショップのシステムがクラウド上で動作している場合、わずかな障害でも売り上げに大きな影響を与える可能性があります。
このようなシステム障害が発生した場合、業務が止まり、クライアントやユーザーに多大な影響を及ぼします。
これに対処するためには、迅速かつ正確な判断が求められます。
障害対応は単なる技術力だけでなく、冷静さと的確な判断力も試される場面です。
クラウド上のシステムは24時間365日稼働しているため、障害対応は夜間や休日に発生することも珍しくありません。
例えば、システムエラーが深夜に発生し、緊急で復旧作業を行う必要がある場合、エンジニアはその瞬間に対応を求められます。
こうした状況では、家族や友人との予定を急遽変更せざるを得ないこともあります。
また、システムの可用性を維持するための取り組みは、障害が発生しない限り外部からは目立ちません。
しかし、企業活動においては非常に重要な業務であり、不可欠な責任を負っています。
こうした責任の重さは、エンジニアにとって大きなプレッシャーとなる一方で、やりがいにもつながります。
障害を解決し、システムを復旧させた瞬間の達成感は、他の職種では味わえない特別なものです。
ただし、ストレスを管理する能力が求められる点は、あらかじめ理解しておくべきです。
過度のストレスが蓄積すると、バーンアウトにつながるリスクもあるため、自己管理が重要です。
プレッシャーの多い職場環境でも、適切なメンタルケアや同僚とのサポート体制があると、こうした課題を乗り越えやすくなります。
クラウドエンジニアやめとけな理由③業務範囲が広く何でも屋になりがち
クラウドエンジニアの業務範囲は非常に広く、多くの場合、1人のエンジニアが複数の役割を担うことになります。
インフラ設計や構築、運用保守に加え、セキュリティやコスト管理、さらにはクライアントとの調整まで求められる場合もあります。
このような業務範囲の広さは、エンジニアにとって挑戦のしがいがある一方で、自分の専門性を深める時間を持つことが難しいと感じる要因にもなります。
特に中小規模の企業では、人員が限られているため、クラウドエンジニアが「何でも屋」的な立場になりがちです。
たとえば、プロジェクトの初期段階ではクラウド環境の設計を行い、その後の構築や運用フェーズではトラブルシューティングを担当します。
さらに、クライアントからの問い合わせにも対応する必要があるなど、多岐にわたる業務をこなすことが求められます。
このような状況では、1つの分野に特化する機会が少なくなるため、特定分野のエキスパートを目指す人にとっては不満に感じる場合があります。
一方で、幅広いスキルを持つゼネラリストとして成長したい人にとっては、魅力的な職場環境とも言えるでしょう。
また、業務範囲が広いことで、様々な知識や経験を得ることができるため、長期的なキャリア形成には有利になる側面もあります。
ただし、あまりにも多くのタスクを抱えると、一つ一つの業務の質が低下するリスクもあります。
そのため、業務を効率的に進めるための時間管理能力や優先順位の見極めが重要です。
この課題を解決するためには、自分の強みや専門分野を明確にし、適切なタスクの割り振りを上司やチームと相談することが大切です。
また、クラウドエンジニアの職場によっては、専門分野を尊重し、役割を明確に分けているケースもあります。
そうした職場を選ぶことで、自分のキャリアに合った環境で働くことが可能になります。
クラウドエンジニアやめとけな理由④成果が目に見えづらい
クラウドエンジニアの仕事は、その性質上、目立ちにくい成果を求められることが多いです。
企業のインフラを支える役割を担うため、システムが正常に稼働しているときこそ、エンジニアの仕事が評価されにくいという特徴があります。
これは、システムが安定している状態が「当たり前」として見られてしまうことが原因です。
例えば、クラウド環境の最適化を行い、コスト削減やパフォーマンス向上を実現したとしても、それが目に見える形で評価される機会は限られています。
エンジニアとしての達成感や満足感を得るためには、自分自身で仕事の意義を感じる力が必要です。
外部からの評価が得られにくい分、チーム内でのフィードバックや自己評価が大切になります。
また、トラブルが発生した際の対応能力は高く評価されますが、それ以外の日常業務では、重要性が認識されにくいこともあります。
このような状況では、自分の成果を適切にアピールするスキルが求められます。
例えば、定期的に実施する業務報告や、プロジェクトの成果を見える化する資料作りを行うことで、自身の貢献度を周囲に伝えることができます。
一方で、システムが安定していること自体が大きな成果であると考える姿勢も重要です。
障害が発生しないこと、業務がスムーズに進むことが、エンジニアの働きの成果であると認識することで、モチベーションを保つことができます。
クラウドエンジニアの仕事は縁の下の力持ちである側面が強いですが、その役割が企業の成功に直結するという点で非常に意義深い職業です。
この特性を理解し、周囲の評価に依存しない自己肯定感を持つことで、仕事に対する満足度を高めることができるでしょう。
クラウドエンジニアが楽しいと感じる瞬間
クラウドエンジニア楽しい理由①新しい技術を試しやすい
クラウドエンジニアの大きな魅力の一つは、最新技術に触れる機会が多いことです。
クラウド業界は日々進化しており、新しいツールやサービスが頻繁にリリースされるため、エンジニアはそれらを学び、試す環境に恵まれています。
特にクラウド環境では、スモールスタートが可能な点が大きな特徴です。
必要最低限のリソースからプロジェクトを始めることができるため、大きなリスクを負わずに新しい技術にチャレンジできます。
たとえば、新しいアーキテクチャを試したり、AIや機械学習のモデルを構築したりといった取り組みが、短時間かつ低コストで可能です。
この柔軟性があることで、エンジニアは失敗を恐れずに試行錯誤することができます。
たとえば、サーバーレスアーキテクチャを使った効率化の実験や、新しいクラウドサービスの導入を検討する際にも、少ないリソースで開始し、必要に応じてスケールアップすることができます。
スモールスタートの文化は、エンジニアにとって大きな安心感を与えます。
同時に、新しい技術を実践的に学ぶ場としても最適な環境です。
実際に試した技術が業務に活用され、業務効率やパフォーマンスが向上する結果を見ることができれば、大きな満足感を得ることができます。
このような自由度と試行錯誤のしやすさは、クラウドエンジニアにとって他の職種では得られない大きなやりがいの一つです。
クラウドエンジニア楽しい理由②自分の設計が形になる満足感
クラウドエンジニアとして、自分が設計したシステムが形になり、実際に稼働する瞬間は、大きな達成感を得られる場面です。
たとえば、新しいクラウド環境を構築し、クライアントがそのシステムを活用してビジネスをスムーズに展開する姿を目の当たりにすることがあります。
「自分の手で作り上げたものが、実際に誰かの役に立っている」と実感できることは、仕事に対する誇りや充実感をもたらします。
このような体験は、日々の努力が報われる瞬間でもあります。
また、システムが順調に稼働しているだけでなく、ユーザーから「使いやすい」「導入して良かった」という声が届くと、さらにモチベーションが高まります。
このようなポジティブなフィードバックは、クラウドエンジニアにとって特別な喜びの一つです。
特に、企業全体の生産性向上やコスト削減に寄与した場合、その効果が具体的な数字として現れることもあります。
たとえば、従来のオンプレミス環境からクラウドに移行し、年間コストを大幅に削減した実績が評価されることがあります。
このような成果が認められると、プロジェクト全体への貢献度が高いと感じられ、やりがいにつながります。
クラウドエンジニアの仕事は、単なる技術的な作業にとどまらず、クライアントの課題を解決し、具体的な価値を提供することに直結しています。
こうしたやりがいを感じられることが、クラウドエンジニアとして働く大きな魅力の一つです。
クラウドエンジニア楽しい理由③PDCAのサイクルが早く面白みややりがいがある
クラウドエンジニアの仕事では、PDCA(計画、実行、評価、改善)のサイクルが非常に早く回る点が特徴的です。
クラウド環境では、従来のオンプレミス環境と比べて、設計から実装、テスト、運用に至るまでのプロセスが短期間で行えるため、迅速な改善が可能です。
たとえば、新しいアプリケーションをクラウド環境で構築した場合、そのパフォーマンスを即座に測定し、フィードバックを基に最適化を進めることができます。
これにより、短期間で効果を確認しながら改良を重ねることができ、エンジニア自身も成長を実感しやすくなります。
こうしたスピード感のある仕事の進め方は、試行錯誤の楽しさと、結果が見えるやりがいを同時に味わえるのが魅力です。
さらに、クラウド環境では、リソースのスケールアップやスケールダウンが容易に行えるため、新しいアイデアやアプローチを気軽に試せる環境が整っています。
これにより、従来の環境では難しかった実験的な取り組みや、効率的なプロトタイピングが可能になります。
エンジニアにとっては、結果を待つ時間が短いため、より多くのプロジェクトに関わりながらスキルを磨けるという利点があります。
また、失敗したとしてもすぐに修正ができる点も、クラウド環境の魅力です。
たとえば、新しいセキュリティポリシーを試した結果が思わしくなかった場合でも、設定を簡単に元に戻し、別の方法を試すことが可能です。
こうした失敗を恐れずに挑戦できる環境は、エンジニアにとって非常に魅力的であり、安心してスキルアップに励むことができます。
このように、PDCAのサイクルが早い環境で働くことは、エンジニアにとってスキルを磨くだけでなく、仕事への充実感を高める要素となります。
クラウドエンジニアで後悔しないキャリア選びのポイント
技術トレンドと自分の興味のバランスを見極める
クラウドエンジニアとして成功するためには、技術トレンドを追い続けることが重要です。
しかし、それ以上に大切なのは、自分の興味やキャリアの方向性に合った分野を選ぶことです。
たとえば、クラウド業界ではAI、ビッグデータ、IoT、エッジコンピューティングなどが注目されていますが、それぞれが求めるスキルや知識、仕事のスタイルは異なります。
そのため、すべての技術を網羅しようとするのではなく、自分がどの分野に最も興味を持ち、熱意を持って取り組めるかを見極めることが大切です。
興味のある分野にフォーカスすることで、学習のモチベーションを維持しやすくなります。
その結果、新しい技術を習得するスピードが上がり、実際のプロジェクトで活かす場面も増えるでしょう。
また、技術トレンドを追うことは重要ですが、すべての最新技術を習得するのは現実的ではありません。
リソースは限られているため、自分のキャリアプランに沿った選択をすることが効率的です。
たとえば、データ分析やセキュリティに特化する、あるいはAIやIoTのクラウド活用に注力するといったように、自分の目指す方向性を明確にすることが重要です。
これにより、専門性を深めながらもトレンドに取り残されることを防げます。
キャリア選びの際には、現在の市場動向だけでなく、将来性や自分の価値観との一致も考慮することが必要です。
例えば、DX推進が進む中で需要が高まる分野に身を置くことで、安定したキャリアを築くことができます。
特定のクラウドプロバイダーに依存しすぎず長期的なスキルセットを意識する
クラウドエンジニアは、AWS、Google Cloud、Microsoft Azureなどの主要プロバイダーの技術に精通することが求められます。
しかし、特定のプロバイダーに特化したスキルだけを持つことは、キャリアの選択肢を狭めるリスクがあります。
一つのプロバイダーに特化した知識は即戦力として高く評価されますが、そのプロバイダーが市場シェアを失った場合、転職先の選択肢が限られる可能性があります。
このため、クラウド全般に通用する汎用的なスキルを意識的に身につけることも大切です。
たとえば、インフラ自動化ツール(TerraformやAnsibleなど)やコンテナ技術(DockerやKubernetes)、セキュリティのベストプラクティスなどは、どのプロバイダーでも活用できるスキルです。
また、マルチクラウドやハイブリッドクラウドの導入が進む現代では、複数のクラウド環境を効率的に管理できるスキルがますます重宝されています。
一つのプロバイダーに依存せず、より柔軟なキャリアを築くことが可能になります。
さらに、長期的な視点でスキルを構築することも重要です。
たとえば、クラウドアーキテクチャ全体を設計する能力や、ビジネスニーズを技術的な解決策に翻訳するスキルは、どの業界でも高く評価される資質です。
こうしたスキルを持つことで、プロバイダーに依存しない汎用性の高いエンジニアとして市場価値を高めることができます。
ソフトスキルも意識する
クラウドエンジニアに求められるのは、技術スキルだけではありません。
クライアントや同僚とのコミュニケーション能力、プロジェクトの進行を円滑にする調整力といったソフトスキルも、キャリアを成功に導く重要な要素です。
たとえば、プロジェクトの要件をクライアントから正確に聞き取り、その要件を技術的な提案に落とし込むスキルが求められます。
また、複雑な問題を解決する際には、チームメンバー間の連携が不可欠です。
これらのソフトスキルが不足していると、優れた技術を持っていてもプロジェクトを成功に導くことは難しくなります。
さらに、技術スキルとソフトスキルの両方をバランスよく身につけることで、単なるエンジニアとしてではなく、プロジェクトをリードするポジションにステップアップする可能性が広がります。
こうしたリーダーシップスキルを持つエンジニアは、組織内での評価が高まり、キャリアパスの選択肢も増えるでしょう。
ビジネスの視点を持ちながら技術を活用できる人材は、クラウドエンジニアとしてだけでなく、経営や戦略の領域でも活躍する可能性があります。
そのため、技術スキルとソフトスキルをバランスよく磨き、後悔のないキャリアを築くことが大切です。
クラウドエンジニアに向いている人の特徴
クラウドエンジニアに向いている人①変化を楽しめる柔軟な思考を持つ人
クラウドエンジニアとして働くためには、絶え間なく進化する技術に対応する柔軟な思考が欠かせません。
クラウド技術は非常にスピード感があり、新しいツールやサービスが日々登場します。
これに対応するには、変化を負担と感じるのではなく、楽しみとして捉えられる姿勢が重要です。
たとえば、現場では既存のシステムを刷新するプロジェクトや、新しいアーキテクチャを導入する案件が頻繁に発生します。
こうした状況で柔軟に対応し、新しい挑戦を楽しむことができる人は、クラウドエンジニアとして大きな成果を上げることができます。
また、技術だけでなく、クライアントのニーズやプロジェクトの要件が変化する場面も多くあります。
こうした変化にも柔軟に対応し、最適な解決策を見つけ出せる人は、職場やクライアントからの信頼を得やすくなります。
クラウド業界では、同じ業務を繰り返す安定感よりも、常に新しい課題に挑むことを楽しめる人が求められます。
変化に対応する力は、クラウドエンジニアとして成功するための基本的な素養と言えるでしょう。
クラウドエンジニアに向いている人②問題解決能力が高く学ぶ意欲がある人
クラウドエンジニアの業務には、複雑な問題を解決する力が求められます。
システムの設計ミスやセキュリティの脆弱性、障害発生時のトラブルシューティングなど、現場では様々な課題が発生します。
こうした問題に対して冷静に対処し、根本原因を見つけ出して解決できる能力は、クラウドエンジニアにとって非常に重要です。
また、技術の進化が速い業界であるため、学ぶ意欲があることも不可欠です。
たとえば、新しいクラウドサービスがリリースされた際に、その仕組みや活用方法を積極的に学ぶことで、競争力を維持することができます。
学び続ける姿勢を持つことで、どんなプロジェクトにも対応できるスキルを身につけることができます。
特に、自主的に調べたり、トレーニングに参加したりといったアクティブな学習スタイルを持つ人は、クラウドエンジニアとしての成長が早いです。
この業界では、自分で考え、自分で学ぶ力が成功への鍵となります。
クラウドエンジニアに向いている人③コスト意識がある人
クラウドエンジニアは、技術だけでなく、コスト管理にも気を配る必要があります。
クラウドサービスは従量課金制が主流であり、設計や運用のミスがコストの増大につながることがあります。
たとえば、不要なリソースを放置したり、最適化されていない構成を使用すると、企業にとって大きな負担になる可能性があります。
そのため、コスト意識を持ち、効率的な設計や運用を心がけることが重要です。
たとえば、オートスケーリングの設定や、適切なリソースの選定を行うことで、パフォーマンスを維持しつつコストを削減する工夫が求められます。
また、クライアントに提案を行う際にも、技術的なメリットだけでなく、コスト面での優位性を示すことで、信頼を得やすくなります。
コスト意識を持つ人は、単なる技術者ではなく、ビジネスの観点からも価値を提供できるエンジニアとして高く評価されるでしょう。
クラウドエンジニアの将来性と需要
クラウド市場の拡大により需要はますます増加
クラウド市場は、近年ますます拡大しており、それに伴いクラウドエンジニアの需要も急速に高まっています。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進により、多くの企業が従来のオンプレミス環境からクラウドへの移行を進めています。
特に、中小企業から大企業まで幅広い業種でクラウドの活用が進んでおり、クラウドエンジニアはその移行プロセスにおいて欠かせない存在です。
市場調査によれば、クラウド関連の市場規模は毎年10%以上の成長を続けており、今後数年でさらに拡大すると予測されています。
この成長に伴い、クラウドエンジニアに対する需要は、他のIT職種を上回るスピードで増加しています。
たとえば、新しいアプリケーションをクラウド上で運用するための設計や、既存システムをクラウド環境に最適化する作業など、多岐にわたる業務が求められています。
さらに、クラウド市場の拡大に伴い、エンジニアが持つべきスキルの幅も広がっています。
AIやIoT、ビッグデータなどの先端技術をクラウド上で活用するプロジェクトが増えており、これらの技術に精通したエンジニアは特に需要が高いです。
このように、クラウドエンジニアの需要は今後も拡大を続け、キャリアの選択肢が広がる職種と言えるでしょう。
マルチクラウド・ハイブリッドクラウドの需要拡大
最近では、複数のクラウドサービスを組み合わせて運用する「マルチクラウド」や、オンプレミスとクラウドを併用する「ハイブリッドクラウド」の導入が進んでいます。
これにより、クラウドエンジニアにはさらに高度なスキルが求められるようになっています。
たとえば、AWS、Google Cloud、Microsoft Azureなど、異なるプラットフォーム間でのデータ統合や運用管理を行うスキルは、企業にとって非常に重要です。
マルチクラウド環境では、各プラットフォームの強みを活かしながら、コスト効率やセキュリティを最大化する設計が求められます。
また、ハイブリッドクラウドでは、オンプレミス環境との連携が鍵となるため、クラウドだけでなく、従来のインフラに関する知識も重要です。
こうした複雑な環境を管理できるクラウドエンジニアは、企業にとってなくてはならない存在となります。
さらに、これらのスキルを持つエンジニアは、一般的なクラウドエンジニアよりも市場価値が高く、給与やキャリアの面で有利になることが多いです。
新しい技術分野でのクラウドの重要性
クラウドは、AIや機械学習、IoT、エッジコンピューティングといった新しい技術分野でも重要な役割を果たしています。
たとえば、AIモデルのトレーニングには、大量のデータを効率的に処理できるクラウド環境が不可欠です。
また、IoTデバイスが生成する膨大なデータを収集、分析する際にも、クラウドはその基盤として機能します。
さらに、エッジコンピューティングでは、クラウドとエッジデバイス間でのデータのやり取りや、負荷分散の管理が重要です。
これらの技術分野でクラウドを活用するプロジェクトは増加しており、クラウドエンジニアには新しいスキルセットが求められています。
こうした先端技術に関わる仕事は、エンジニアにとって大きなやりがいと成長の機会を提供します。
さらに、これらの分野での経験を積むことで、市場価値の高いエンジニアとしてキャリアを築くことができます。
まとめ:クラウドエンジニアはやめとけと言われることもあるが将来性のある職種
クラウドエンジニアは、技術の進化が速く、責任の重さや広範囲な業務内容に直面するため、「やめとけ」と言われることもあります。
しかし、その一方で、新しい技術を試せる環境や、自分が設計したシステムが形になり活躍する達成感、PDCAのサイクルが早く成果を実感しやすい点など、やりがいや楽しさも多い職種です。
また、クラウド市場の拡大に伴い、クラウドエンジニアの需要はますます高まっています。
特に、マルチクラウドやハイブリッドクラウドの管理スキルや、AIやIoTといった先端技術との組み合わせが注目される中で、エンジニアの市場価値はさらに向上するでしょう。
クラウドエンジニアとして後悔しないキャリアを築くためには、技術トレンドを追いながらも、自分の興味やキャリアの方向性を見極めることが重要です。
さらに、特定のクラウドプロバイダーに依存しない汎用的なスキルの習得や、ソフトスキルの強化も必要です。
変化を楽しむ柔軟な思考や、問題解決能力、コスト意識を持つ人には、クラウドエンジニアは非常にやりがいのある職種と言えます。
技術的なスキルとソフトスキルをバランス良く身につけ、将来の需要を見据えたスキルセットを構築することで、クラウドエンジニアとしてのキャリアを長期的に発展させることが可能です。
クラウドエンジニアとして働くことで得られるやりがいと成長の機会を最大限に活かすため、ぜひこの記事を参考に、次のキャリアの一歩を踏み出してください。